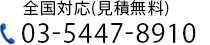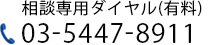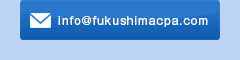Information
福島公認会計士事務所 HOME > 日本相続税
日本相続税
平成25年度相続税改正の背景
相続税の課税方式は昭和33年に改正されて以来、ほとんど基礎控除・配偶者控除・税率等を通じて軽減の歴史をたどってきました。特に、バブル期に地価が急騰し、多くの人の相続税の負担が過重になったことから、負担を軽減すべく、基礎控除を引き上げ、税率構造を緩和し、特例措置を大きく拡充するなどの改正が行なわれてきました。
しかし、その後の地価の下落にも関わらず、そのまま据え置かれてきました。その結果、相続税の課税割合は4.1%にまで低下し、平成23年には125万人が死亡して、約5万1千件しか相続税の申告がない状況となっています。
そこで、相続税の「資産再配分機能の回復」を図るため、、地価動向の推移に対応して基礎控除の水準を引き下げることになりました。
また、昭和63年以降累次にわたり、最高税率の引き下げを含む累進構造の緩和が行われ、相続税の資産再配分機能の低下につながっていることから、税率構造の見直しを行なうことになりました。
このようなことから、平成25年度税制改正において、課税ベースの拡大や格差是正を目的に基礎控除の水準を引き下げ、税率構造の見直しを行なうなど、半世紀ぶりの増税ということになりました。
しかし、その後の地価の下落にも関わらず、そのまま据え置かれてきました。その結果、相続税の課税割合は4.1%にまで低下し、平成23年には125万人が死亡して、約5万1千件しか相続税の申告がない状況となっています。
そこで、相続税の「資産再配分機能の回復」を図るため、、地価動向の推移に対応して基礎控除の水準を引き下げることになりました。
また、昭和63年以降累次にわたり、最高税率の引き下げを含む累進構造の緩和が行われ、相続税の資産再配分機能の低下につながっていることから、税率構造の見直しを行なうことになりました。
このようなことから、平成25年度税制改正において、課税ベースの拡大や格差是正を目的に基礎控除の水準を引き下げ、税率構造の見直しを行なうなど、半世紀ぶりの増税ということになりました。
相続税の主な改正点と影響
1.定額控除が3,000万円、法定相続人比例控除が600万円×法定相続人数に引き下げ
(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
相続税の基礎控除のあるべき水準を具体的に考えるに当たっては、物価・地価が現在と同等であった時期(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と同等になるように再設定し、従来の水準の60%に改定することになりました。
これにより、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は改正前の4.1%(平成23年中の年間死亡者数125万人に対して、相続税の申告件数は5万1,409件)から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。
相続税の基礎控除のあるべき水準を具体的に考えるに当たっては、物価・地価が現在と同等であった時期(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と同等になるように再設定し、従来の水準の60%に改定することになりました。
これにより、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は改正前の4.1%(平成23年中の年間死亡者数125万人に対して、相続税の申告件数は5万1,409件)から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。
| 改正前 | 改正後 | |
| 定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続人比例控除 | 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人数を乗じた金額 |
2.最高税率が55%に引き上げられると共に、税率の区分が従来の6段階から8段階に
(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
| 改正前 | 改正後 | ||||
| 各取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) | 各取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) |
| 1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - |
| 3,000万円以下 | 15 | 50 | 3,000万円以下 | 15 | 50 |
| 5,000万円以下 | 20 | 200 | 5,000万円以下 | 20 | 200 |
| 1億円以下 | 30 | 700 | 1億円以下 | 30 | 700 |
| 3億円以下 | 40 | 1,700 | 2億円以下 | 40 | 1,700 |
| 3億円超 | 50 | 4,700 | 3億円以下 | 45 | 2,700 |
| 6億円以下 | 50 | 4,200 | |||
| 6億円超 | 55 | 7,200 |
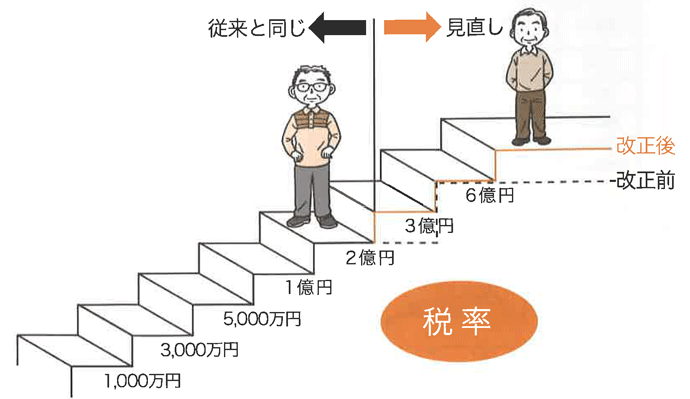
3.基礎控除の引き下げと税率構造の見直しによる影響
基礎控除の引き下げに伴う影響が大きく、遺産額の低い層ほど増税率は高くなります。
1.配偶者と子が相続人である場合(配偶者は法定相続分を相続するものと仮定)
| 課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | ||||||
| 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | |
| 5千万円 | 0 | 40 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - |
| 1億円 | 175 | 435 | 248 | 100 | 315 | 315 | 50 | 206 | 412 |
| 3億円 | 2,900 | 3,460 | 119 | 2,300 | 2,860 | 124 | 2,000 | 2,540 | 127 |
| 5億円 | 6,900 | 7,605 | 110 | 5,850 | 6,555 | 112 | 5,275 | 5,962 | 113 |
| 10億円 | 18,550 | 19,750 | 106 | 16,650 | 17,810 | 106 | 15,575 | 16,635 | 106 |
| 20億円 | 43,550 | 46,645 | 107 | 40,950 | 43,440 | 106 | 38,350 | 41,182 | 107 |
2.子のみが相続人である場合
| 課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | ||||||
| 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | |
| 5千万円 | 0 | 160 | - | 0 | 80 | - | 0 | 20 | - |
| 1億円 | 600 | 1,220 | 203 | 350 | 770 | 220 | 200 | 630 | 315 |
| 3億円 | 7,900 | 9,180 | 116 | 5,800 | 6,920 | 119 | 4,500 | 5,460 | 121 |
| 5億円 | 17,300 | 19,000 | 109 | 13,800 | 15,210 | 110 | 11,700 | 12,980 | 110 |
| 10億円 | 42,300 | 45,820 | 108 | 37,100 | 39,500 | 106 | 33,400 | 34,500 | 103 |
| 20億円 | 92,300 | 100,820 | 109 | 87,100 | 93,290 | 107 | 84,000 | 85,760 | 102 |
4.未成年者控除及び障害者控除の控除額の引き上げ
(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
物価の動向(昭和63年を100とすると、平成22年は112.3)及び今回の相続税全体の見直し内容を踏まえて、控除額が引き上げられることになりました。
(1)未成年者控除及び障害者控除とは
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当し、かつ未成年者又は障害者に該当する場合に適用される税額控除です。未成年者や障害者は、一般の人より生活費が多くかかることなどを配慮した規定であるといわれ、本人の相続税額から控除できない金額については、扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
*未成年者控除は、制限納税義務者に該当する者を除きます。?障害者控除は、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に該当する者を除きます。
(2)適用対象
法定相続人である未成年者又は障害者が「相続又は遺贈により財産を取得する」ことが要件となっているため、未成年者や障害者本人が相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、これらの控除の適用はなく税額控除を受けることはできません。
物価の動向(昭和63年を100とすると、平成22年は112.3)及び今回の相続税全体の見直し内容を踏まえて、控除額が引き上げられることになりました。
(1)未成年者控除及び障害者控除とは
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当し、かつ未成年者又は障害者に該当する場合に適用される税額控除です。未成年者や障害者は、一般の人より生活費が多くかかることなどを配慮した規定であるといわれ、本人の相続税額から控除できない金額については、扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
*未成年者控除は、制限納税義務者に該当する者を除きます。?障害者控除は、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に該当する者を除きます。
(2)適用対象
法定相続人である未成年者又は障害者が「相続又は遺贈により財産を取得する」ことが要件となっているため、未成年者や障害者本人が相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、これらの控除の適用はなく税額控除を受けることはできません。
| 改正前 | 改正後 | |
| 未成年者控除 | 20歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき6万円 | 20歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき10万円 |
| 障害者控除 | 85歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき6万円(特別障害者については12万円) | 85歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき10万円(特別障害者については20万円) |
5.国外財産に関する納税義務者の範囲の拡大
(平成25年4月1日以降の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用されます)
日本に居住する祖父が国外に居住する日本国籍を有していない孫に国外財産を遺贈した場合、これまで課されなかった日本の相続税が課税されることになります。贈与の場合も同様に贈与税が課されます。
日本に居住する祖父が国外に居住する日本国籍を有していない孫に国外財産を遺贈した場合、これまで課されなかった日本の相続税が課税されることになります。贈与の場合も同様に贈与税が課されます。
(1)相続税の納税義務者の区分
相続税又は遺贈により財産を取得した個人は、相続税の納税義務者となります。
相続税又は遺贈により財産を取得した個人は、相続税の納税義務者となります。
| 無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者:相続または遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。 |
| 非居住無制限納税義務者:相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの(その個人またはその相続もしくは遺贈に係る被相続人(遺贈した人を含む)がその相続または遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)。 | |
| 制限納税義務者 | 相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの(非居住無制限納税義務者に該当する人を除く)。 |
| 特定納税義務者 | 贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記無制限納税義務者および制限納税義務者に該当する人を除く)。 |
(2)納税義務者別の課税財産の範囲
従来の制度では、子や孫等に外国籍を取得させることにより、国外財産への課税を免れるような租税回避事例が生じていたため、日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しない者が、日本国内に住所を有する者から相続もしくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加えることにしました。
従来の制度では、子や孫等に外国籍を取得させることにより、国外財産への課税を免れるような租税回避事例が生じていたため、日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しない者が、日本国内に住所を有する者から相続もしくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加えることにしました。
| 納税義務者の区分 | 課税される財産 | |
| 無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者 | 国内財産、国外財産および相続時精算課税適用財産 |
| 非居住無制限納税義務者 | ||
| 制限納税義務者 | 国内財産および相続時精算課税適用財産 | |
| 特定納税義務者 | 相続時精算課税適用財産 | |
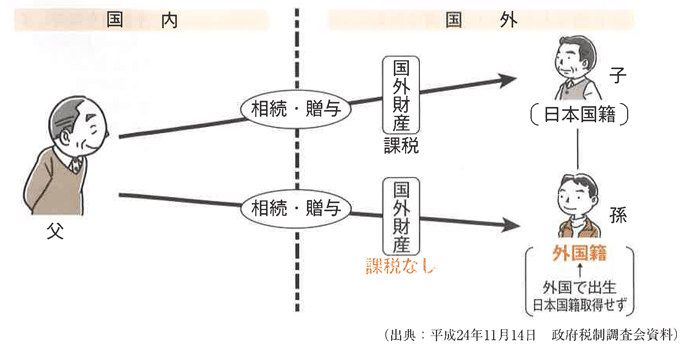
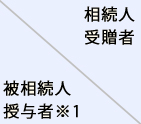 | 国内に住所あり | 国内に住所なし | |||
| 日本国籍あり※2 | 日本国籍なし | ||||
| 5年以内に 国内に住所あり | 左記以外 | ||||
| 国内に住所あり | 居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税) | 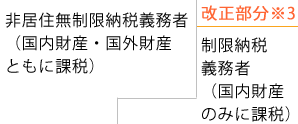 | |||
| 国内に 住所なし | 5年以内に 国内に住所あり | ||||
| 上記以外 | |||||
6.特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充と適応要件の緩和
相続税の基礎控除が引き下げられた反面、負担軽減のために小規模宅地等の特例の適用範囲が見直されました。これにより、地価の高い所で居住している場合や事業を行なっている場合の一定の宅地等では、相当額の相続税の負担軽減になると予想されます。
(1)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限を拡充し、かつ特例の対象として選択する宅地等の全てが、特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算は従来通り調整が行われます。
(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
(1)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限を拡充し、かつ特例の対象として選択する宅地等の全てが、特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算は従来通り調整が行われます。
(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
| 改正前 | 改正後 |
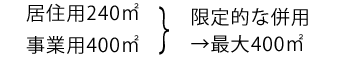 | 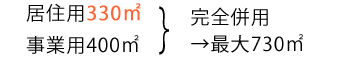 |
(2)一棟の建物で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分は特例の対象となります。これにより、特例の適用を受けられる人が多くなります。
(平成26年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
(平成26年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
| 改正前 | 改正後 |
| 例えば、二世帯住宅について、住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合は、特例の適用要件である「同居」として認められない。 | 例えば、二世帯住宅の構造上の要件を撤廃し、住宅内部で行き来ができるか否かに関わらず、「同居」として認められる。 |
(3)老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等が、①被相続人に介護が必要なため入所したものであること②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと、の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例を適用できるようになります。
(平成26年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
(平成26年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます)
7.非上場株式等に係る納税猶予制度の適用要件の緩和
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、より使いやすくするために、見直しが行われました。具体的には、納税猶予制度活用の最大の障害であった雇用確保要件を「毎年8割以上」から「5年平均で8割以上」とする他、手続の簡素化や事務負担の軽減など、実態に即した要件緩和が図られました。
1.適用要件の緩和
| 項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
| ①経営承継相続人等の要件 | 後継者を先代経営者の親族に限定 | 先代経営者の親族外承継を対象化 | ○ | ○ |
| ②贈与者の要件 | 贈与時において役員でないこと | 贈与時において代表権を有していないこと | - | ○ |
| ③経営贈与承継期間内に贈与者が役員になって給与を受けた場合 | 贈与税の納税猶予の取消自由に該当 | 贈与税の納税猶予の取消自由に該当しない (有給役員として残留可) | - | ○ |
| ④経済産業大臣の認定の 有効期間(5年間)における 常時使用従業員数 | 雇用の8割以上を「5年間毎年」維持 | 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価 | ○ | ○ |
| ⑤株券発行会社 | 原則として株券を発行し、担保(法務局に供託)に供すること | 株券の発行をしなくても、納税猶予の適用を認める | ○ | ○ |
2.負担の軽減
| 項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
| ①民事再生計画の認可決定等があった場合 | 相続・贈与から5年後以降は、 後継者の死亡または会社倒産により納税免除 | その時点における株式等の価格に基づき納税猶予税額を再計算し、その税額の納税猶予を継続する(一部免除) | ○ | ○ |
| ②被相続人の債務および葬式費用 | 特例非上場株式等の価格から控除 | 特例非上場株式等以外の相続財産から控除 | ○ | - |
| ③雇用確保要件が満たされないために認定が取り消された場合 | 納税猶予税額を全額金銭納付する | 納税猶予税額について、延納または物納の適用を選択することができる | ○ | 延納のみ ○ |
| ④経済産業大臣認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合 | 納税猶予期間を含む全期間における利子税を納付しなければならない | 納税猶予期間(5年間)中の利子税を免除する | ○ | ○※ |
※納税猶予税額の全部または一部を納付する場合の利子税は、「延滞税等の見直し」により、納税猶予期間中の利子税の割合が年0.9%(特例基準割合が2%の場合)に引下げられます。
3.手続の簡素化
| 項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
| ①申告書、継続届出書等に係る添付書類 | 提出が必要 | 一定のものについては、提出を要しない | ○ | ○ |
| ②経済産業大臣による 事前確認制度 | 制度利用の前に、「認定」に加えて「事前確認」を要する | 「事前確認」の制度を廃止する | ○ | ○ |
4.適正化
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 | |
| ①上場株式等 (1銘柄につき3%以上) を認定会社である資産保有型会社等が保有する場合 | 納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を含めて計算する | 納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を含めず計算する | ○ | ○ | |
| 適用対象となる資産保有型会社等の要件 | ②常時使用従業員数が5人以上とする要件 | 経営承継相続人等と生計を一にする親族を含む従業員数で判定 | 経営承継相続人等と生計を一にする親族以外の従業員数で判定 | ○ | ○ |
| ③3年以上継続して行う商品販売等における「資産の貸付け」の範囲 | 制限なし | 経営承継相続人等の同族関係者等に対する貸付けを除外 | ○ | ○ | |
| ④総収入金額がゼロとなった場合 | 総収入金額は営業外収益および特別利益を含めて判定 | 総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益を除外 | ○ | ○ | |